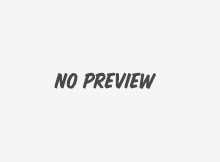Japan
In this article, the writer talks about TV and how we waste our time watching TV shows that we are not even interested. When you come home after
Read More
Japan
私の目覚める場所はどこ? ー社会学と日常生活ー 最初に「私」が朝、目を覚ますところから始めよう。「私」が目を覚ます場所はたいてい、私の家の私の部屋(私のアパート)の私のベットの上。むろん「私」はこの部屋に愛着を感じている。「私の匂い」がしみついたさまざまな物。受験時代からの「戦友」の机。部屋の隅のざっし。みんな「私の歴史」だ。これ意外のどこにこんなに居心地のよい場所があるだろうか? だから、君が毎日自分の家にきちんと帰ってくるのは、「あたりまえ」であるように思える。でも君が毎日夜にはきちんと家に帰っているのは、本当に居心地がよいためだろうか?愛着があるからだけだろうか?一生は短いのに、毎夜、判で押したように家に帰る人が多いということは、実に不思議なことだと考えたことはないだろうか。 けれども、実際に帰らないとすると、実に面倒なことが多いということも、君は知っているはずである。家族やルームメイトと暮らしている場合には、まず「今日は帰らない」という連絡をしなければならないと思うだろう。連絡すれば必ずなぜ帰らない(帰れない)のかという理由を聞かれるはずだ。そう、「私の目が覚める場所」に関心を持っているのは、「私」だけではない。親や下宿先のおばさん、ルームメイトやパートナーなど、色々な人が「私」の居場所に関心をもっている。 このことを知っているということが、「私」をこの部屋に帰らせている重要な理由の一つなのだということに気がつくはずだ。(略) 私たちは、家族は互いに他の家族について知っているべきだと考えている。何年も連絡しあわなくたって友達は友達だ、という考えはありえても、家族なのに何年も連絡一つないとか、連絡もせずに外国に行ってしまったなんていうことがあれば、私たちは「へえっ。変な家族。」とか「変な親子。縁を切ったのかな」なんて思ってしまう。(略) 他方、「家族以外の他者」にとっては、「私の寝る場所」は、連絡先としての意味をもつ。誰かが「私」に何かを伝えたい場合にはどうすればよいのかということをきちんと知らせておくことが、しっかりした人間関係の基礎であると私たちは考えている。(略) しかし、それだけではない。もし「私」が女であるなら、「私の寝る場所」への他者の関心のなかに「性関係」の「存在(不在)証明」という側面があることにとっくに気づいているに違いない。そう、これは完全にジェンダーのテーマだ。たいていの社会では日常会話においては「性のタブー」が存在する。この礼儀場の「性のタブー」は、「性関係の存在(不在)証明」を、直裁的に呈示することを困難にする。 その結果、「性関係の存在(不在)証明」は「私の寝る場所」という、より曖昧な証拠によって呈示されることになる。むろん、性に関わる意識は時代と社会によって多様であるから、いちがいにはいえない。しかし、少なくとも現代の日本社会では、公的に表明された「性関係」(独身であるか配偶者をもつかにかかわらず)と一致しない「性関係」に対する社会的制裁は、女性により強く加えられる。すなわち、女性の「性関係」に対して人々の後期品はより強く働くのである。このことは女性の行動に対してより多くの「制約」を導きがちである。例えば、独身の女性は、「性関係の存在」自体が人々の好奇心の的になることを避けることができないにもかかわらず、しかも「性関係の不在証明」を呈示しなければならない。これが女性が「外泊」することに対するさまざまな「制約」の意味である。「なぜ悪いのか」という理由の呈示がないままに、「女が黙って外泊することは悪いことだ」という言葉を、何度女性は聞かされたことか。まだ「性への関心」も目覚めないほんの少女の時から、両親は女性にこの言葉をいい聞かせることが多い。そして、「どうして」なんて聞こうものなら「なんてことを言うの」とこぴっどく叱られるのである。女性はこうして、自分の行為には根拠がないことでも、「ひどく悪いこと」があるのだということを「知らされる」のである。
Read More